雨宿り
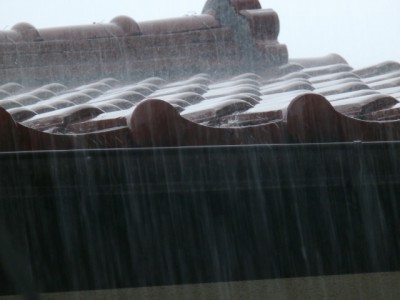
ある日の暮方のことである。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。
雨は羅生門をつつんで、遠くから、ざっという音をあつめて来る。夕闇はしだいに空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜につき出した甍の先に、重たくうす暗い空を支えている。
― 芥川龍之介 「羅生門」―
・・・・・たとえば、こんな日だったのであろうか。
そんなことを思わせる雨が、さっきから向かいの家の屋根に白いしぶきをはね上げ、空は夕暮れに向かおうとしている。
「こんな日」というのは、羅生門の下に下人が雨宿りした日のことだ。
もっとも、あの丹塗(にぬり)の柱には蟋蟀(きりぎりす)がとまっていたのだから、あれは秋の雨だった。
今読み返してみると、
夕冷えのする京都は、もう火桶が欲しいほどの寒さである。
と書いてある。
晩秋、あるいは初冬の雨だ。
梅雨の走りの、今頃の雨ではない。
下人は雨のやむのを待っている。
待ってはいるが、雨が止んだとて、別に行く先なぞないのだ。
物語はそんな行き先を失くした若い下人の話だ。
今読んでみて、彼の文章がとてつもなくうまいのに感心する。
それなのに、読み終えて、何ほどの感動があるわけではない。
ふしぎだ。
それは、私がすでに話の筋をよく知っているからであろうか。
たぶん、そうではないのだ。
芥川は 《 ほんとうに行く先がなくなってしまった人間 》 のことがわからなかったのだ。
たぶん、そういうことなのだ。
「では、おまえが言う 《 ほんとうに行く先がなくなってしまった人間 》 とは、どんなものか」
などと問われても、はなはだコマルが
「山椒魚です」
などと答えたら笑われるだろうか。
